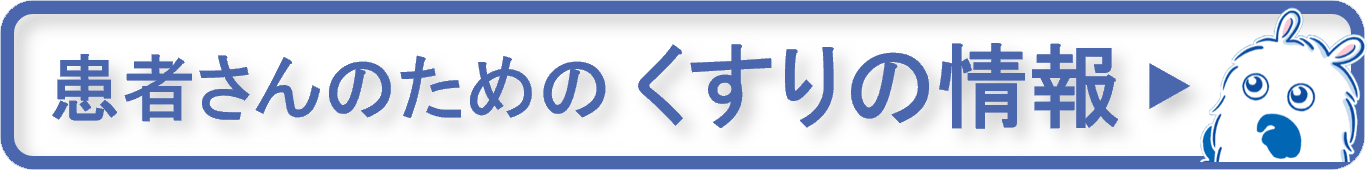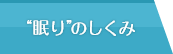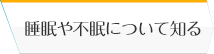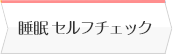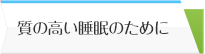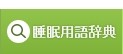眠れないのは歳のせい?
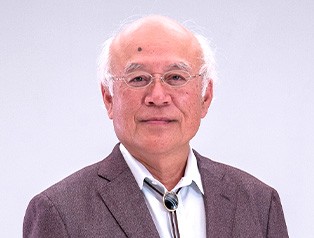
堀口 淳 先生
歳を取ると若い頃のようには眠れなくなってきます。眠れないことで昼間に色々な問題が起こってきます。日常生活で困ることも増えてきます。
不眠症は、いくつもの原因が重なって起こり、様々な症状があらわれます。単なる老化の問題と片付けるのではなく、眠れない原因を考えることが重要です。特に高齢者に見られる睡眠の問題について、その原因と対処方法について解説します。
高齢者に見られる睡眠の問題
- (1)睡眠構造の変化などによる影響
- 睡眠構造とは、睡眠の深さや浅さ、あるいは短さといったもののことを言います。歳とともに睡眠効率が悪くなります。具体的には、睡眠が浅く、睡眠時間も減り、夜中に何度も目が覚めやすくなります。トイレに行った後に床についてもなかなか眠れないといったことも起こります。そのために昼寝や居眠りをしやすくなります。また、体の中の時計、すなわち睡眠のリズムを整える働きがある部位の問題も起こってくるため、早寝早起きとなります。
ただ、若いときのように8時間眠れていないからといって不眠であると考えてはいけません。歳をとってくると6時間ぐらいの睡眠時間が普通です。ですので、睡眠に対する正しい知識を持っておくことが非常に重要です。
- (2)身体の病気や心の病気などによる影響
- 高齢者は歳をとってくると、身体の病気や心の病気が増えてきます。睡眠障害の原因となる代表的な身体の病気としては、高血圧、心疾患、喘息、逆流性食道炎、糖尿病、リウマチ、夜間頻尿などがあげられます。夜寝るときに、足がむずむずしたり、ほてったり、かゆくなったりなど様々な違和感でなかなか寝付けない、むずむず脚症候群という病気も知られるようになってきました。また、うつ病や認知症などの精神疾患も睡眠に影響を及ぼします。さらに、病気だけでなく、治療のために用いられる薬自体でも眠れなくなってしまう場合もあります。
睡眠障害を起こす代表的な薬としては、気管支拡張薬、胃腸薬、降圧薬、ステロイド、抗うつ薬などが知られています。疾患の治療のための薬を服用し始めてから、睡眠に関する悩みが生じた場合には、必ず医師や薬剤師に相談しましょう。
よりよい睡眠のために
歳を重ねるごとに1日の睡眠時間が減るのは自然なことです。睡眠時間が短くなっても日常生活において支障がない場合はとくに心配する必要はありません。つまり、昼間眠くなければいいのです。
ただし、工夫することで睡眠の質を改善することは可能です。
- 昼と夜のメリハリをつけるため、日中に日光を浴びて適度な運動をしましょう。
- ⇒体の中の時計は、朝、太陽の光を浴びて目に光が入ったときから1日のリズムをきざみ始め、その約15時間後に眠くなるといわれています。早すぎる時間に光が目に入ると、夜は早い時間から眠くなってしまいます。極端に早く目覚めた朝は、太陽の光を浴びないようサングラスを着用するようにしましょう。
- 日中に長い時間の昼寝をしないようにしましょう。
- ⇒昼寝をする場合は、午後の早い時間帯(30分まで)にしましょう。
- お茶やコーヒー、アルコールの摂取は寝る前には控えましょう。
- 眠気がないのに早い時刻から床に入るのをやめましょう。
- ⇒もし、床の中にいて眠れないようなら一度床から出ましょう。
以上のことに気をつけても、「夜中に何度も目が覚めてしまう」、「朝早くに目覚めてしまう」など不眠の症状が改善しない場合には、専門の医師に相談することをおすすめします。